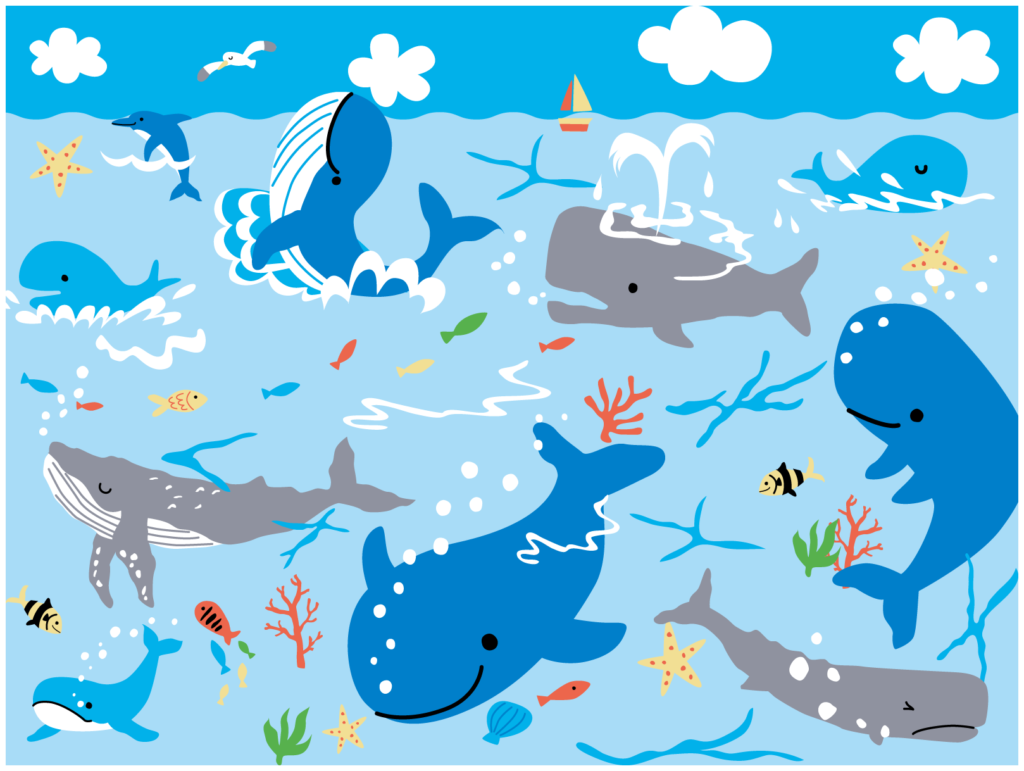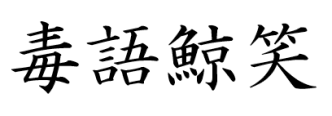(66)・・・諦感・・・
若い女性が逝ってしまった。止めることが出来なかった。
いつも、部屋から出ず、一人で暮らしていた。両親はいたのだが、心を通わせることはなかった。「どうせ、わかってもらえんけん」。
いつも、繊細な絵を描いていた。月に一回は、きちんと通院し、時にくじらの絵を呉れた。微笑みを絶やさず、しかし、人を信じることができず、世の中を怖がっていた。絵は、ファンタジーだったから、憧れだったのだろう。
漢方は、きちんと飲まなかった。眠剤だけは、飲んでいたと思う。語弊があるが、幻聴や妄想があった方が、まだ紛れたかもしれない。いつもクリアな頭で、生きることの辛さや虚しさを、淡々と話していた。「希望はありますよ。どこかに住みよい場所があるかも知れんけん」と、力無く笑っていた。
衝動行為じゃなかったと思う。おそらく、従容として逝ったのだろう。何も出来なかった僕の、あまりの無力が情けなかった。老身には堪えて、2日間、熱が出た。
やはり、「働けないこと」「社会に出ていないこと」で、自分を責め、どこか卑下していたと思う。「ひきこもりも人生」、「仕方なく働けない人もたくさん居るけん、構わんのよ」などと言っても、慰めにもならず、簡単には届かない。未だ、「働かざるもの食うべからず」という風潮は、田舎ほど根強いのだ。合掌。